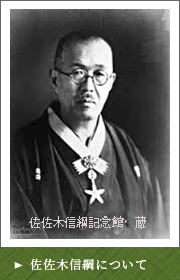佐佐木信綱
 歌人・国文学者として大きい足跡を残した佐佐木信綱は、明治5年(1872) 6月3日、鈴鹿市石薬師町で生まれた。
歌人・国文学者として大きい足跡を残した佐佐木信綱は、明治5年(1872) 6月3日、鈴鹿市石薬師町で生まれた。
信綱の家は代々医者・学者であったが、祖父徳綱は書家で武術にも秀で「東海道人物誌」に紹介されるほどであった。また、父弘綱は本居宣長の流れを汲む伊勢の国学者・足代弘訓に学び、江戸から明治にかけて歌人・国学者として全国的に活躍し、門弟は約1600名に及んだともいわれる。
信綱は、父の指導の下に満4歳の時万葉集、古今集、山家集の名歌を暗誦、5歳には孝経の素読をした。5歳のときには、信綱かるたにもある次の歌を作っている。
明治10年(1877)12月、父が鈴屋社中の招請により一家は松阪へ移住した。翌年湊町小学校に入学した。
明治15年(1882)一家は上京。明治17年(1884)東京大学文学部古典科に12歳で入学し、同21年(1888)16歳で卒業した。卒業後は宮仕えはしないという父の考えを継ぎ、生涯文筆生活であった。東京大学で教えているが、非常勤講師としてである。
昭和38年(1963)12月2日、熱海市西山の凌寒荘にて没した。享年91歳。
佐佐木信綱年譜
| 西暦 | 数え年 | ことがら |
|---|---|---|
| 1872 (明治5年) | 1歳 | 6月3日鈴鹿市石薬師町(現在)に佐々木弘綱の長男として誕生。 |
| 1977(明治10年) | 6歳 | 松坂へ。 |
| 1882(明治15年) | 11歳 | 東京へ。 |
| 1884(明治17年) | 13歳 | 東京大学に入学。 |
| 1896(明治29年) | 25歳 | 雪子(2歳年下)と恋愛結婚。 |
| 1897(明治30年) | 26歳 | 短歌結社・竹柏会発足 |
| 1898(明治31年) | 27歳 | 竹柏会機関誌「心の花」発行。 |
| 1899(明治32年) | 28歳 | 竹柏会第一回大会、日本橋倶楽部で。 |
| 1901(明治34年) | 30歳 | 「夏は来ぬ」『新選国民唱歌』に発表。 |
| 1903(明治36年) | 32歳 | 第一歌集『思草』出版。中国旅行。 |
| 1905(明治38年) | 34歳 | 東京帝国大学の講師になる。 |
| 1908(明治41年) | 37歳 | 父弘綱の碑が故郷の淨福寺に建つ。 |
| 1925(大正14年) | 54歳 | 『校本万葉集』完成。 |
| 1927(昭和2年) | 56歳 | 『新訓万葉集上下』出版。 |
| 1932(昭和7年) | 61歳 | 還暦記念として「石薬師文庫」寄贈。 |
| 1937(昭和12年) | 66歳 | 第1回文化勲章を受章。芸術院会員。 |
| 1944(昭和19年) | 73歳 | 熱海市へ。「凌寒荘」に住まう。 |
| 1948(昭和23年) | 77歳 | 愛妻雪子が亡くなる。享年75歳。 |
| 1953(昭和28年) | 82歳 | 自伝三部作を書きあげる。 (昭和28年9月〜昭和36年1月) 『ある老歌人の思ひ出』 『作歌八十二年』 『明治大正昭和の人々』 |
| 1963(昭和38年) | 92歳 | 12月2日、亡くなる。 |
| 1970(昭和45年) | – | 鈴鹿市は生家を移築し、佐佐木信綱記念館とする。 |
歌人としての活躍
歌集として「思草」「新月」「常盤木」「天地人」「山と水と」などがある。作風は、清新、温雅、肯定的人生観がうかがえる。「ひろく ふかく おのがじしに」を作歌信条として、多くの歌人を育てており、石槫千亦、川田 順、木下利玄、前川佐美雄、九条武子、柳原白蓮、五島美代子などは信綱の門人である。
学者としての業績
大学を卒業して間もない17歳での出版「日本文範」を第一歩として、生涯研究を続け数えきれないほどの著書を刊行している。その業績は、①万葉集の研究、②歌学史に関する研究、③文献発掘の3分野である。
① 橋本進吉等の協力を得て、原本のない万葉集について多くの古写本を調べ上げて集大成し、万葉集研究の基礎を確立したとされる「校本万葉集」を刊行した。30歳台にして早くも万葉学の権威となっており、「評釈万葉集」「新訓万葉集」「万葉事典」など万葉集に関する著作物が多い。
② 不朽の名著といわれる「日本歌学史」「和歌史の研究」など、歌学史研究に関する多数の著書を残している。
多様な分野での足跡
校歌:120以上の学校の校歌作詞 (詳細は下記)
筝曲・長唄・一弦琴・音頭などの作詞、歌舞伎・オペラなどの脚本
「松阪の一夜」:元文部省小学校国語教科書に掲載(賀茂真淵と本居宣長の会見の文)
刊行された主な著作
歌集(生涯一万首以上といわれる)
|
思草 遊清銀藻 新月 銀の鞭 常盤木 豊旗雲 鶯 椎の木 天地人 瀬の音 黎明 山と水と 秋の声 老松 |
自伝三部作
| ある老歌人の思ひ出 作歌八十二年 明治大正昭和の人々 雲(随筆) |
万葉集関係
| 校本万葉集 万葉読本 評釈万葉集 新訓万葉集 白文万葉集 万葉辞典 |
解説書
|
金沢本万葉集 有栖川王府元暦万葉集 桂本万葉集 西行上人歌集 百人一首講義 |
校註
|
校註徒然草 校註竹取物語 校註伊勢物語 校註土佐日記 校註方丈記 校註更級日記 |
啓蒙書(入門書)
| 和歌を志す夫人の為に 短歌入門 作歌辞典 和歌ものがたり |
三重県内の信綱歌碑
三重郡朝日町
小向神社
役場入口
三重郡菰野町
尾高観音
湯の山温泉
四日市市
光念寺
志摩市
志摩観光ホテル
伊賀市
上野城天守閣天井
鈴鹿市<石薬師地区外>
鼓ケ浦海岸
近鉄若松駅前
文化会館前
鈴鹿市<石薬師地区内>
佐佐木信綱記念館 3
大木神社 1
石薬師寺 1
蒲桜 1
うのはな街道 2(1か所)
佐佐木家墓地 1
信綱揮毫の万葉歌碑
近鉄名張駅前
四日市北警察署隣り
作詞した校歌
<北海道>
愛別町立愛別中学校
<福島>
会津坂下町立広瀬小学校
<茨城>
日立市立宮田小学校 大子町立黒沢小学校 水戸市立城東小学校 水戸市立浜田小学校
<栃木>
那須烏山市立烏山小学校
<埼玉>
浦和高等女学校 与野農商学校 本庄市立児玉中学校 滑川町立宮前小学校 滑川町立滑川中学校 川口市立本町小学校 久喜市立江面第一小学校
<千葉>
銚子市立船木小学校 同第一中学校 同飯沼小学校 松戸市立第五中学校 松戸市立東部小学校 佐原市立第二中学校 県立子金高校 県立茂原農学校 香取郡神崎町立神崎小学校
<東京都>
板橋区立赤塚第三中学校 港区立神明小学校 北区立志茂小学校 千代田区立麹町中学校 都立豊島高校 品川区立山中小学校 筑波大学附属小学校 台東区立根岸小学校 府立第七高等女学校 府立第十高等女学校 山中国民学校 烏山国民学校 根津尋常小学校 日本赤十字看護大学 杉並区立桃井第三小学校 世田谷区立緑丘中学校 東京薬学専門学校女子部
<神奈川>
横浜市立大綱小学校 同間門小学校 同南中学校 同末吉中学校 大正中学校 同戸塚高校 横浜第一中学校 同横浜平沼高校 鎌倉町立鎌倉実科高等女学校 県立三崎高校 県立川崎中学校 川崎市立幸町小学校 川崎市立旭町小学校 鎌倉市立御成小学校 湯河原町立湯河原中学校
<福井>
小浜市立国富小学校
<山梨>
玉穂町立三村小学校
<長野>
長野清泉女学院中学高等学校
<静岡>
静岡市立安倍川中学校 玉川中学校 大里中学校 熱海市立熱海中学校 福田町立福田小学校 同福田中学校 浜松市立西部中学校 同南陽中学校 浜松海の星高校 県立静岡工業高校 御殿場市立神山小学校
<愛知>
県立豊川工業高校 豊川市立南部中学校 中京大学附属中京高校
<岐阜>
県立武義高校 同岐阜農林高校 同本巣高等女学校 同岐阜高等女学校 高山市立南小学校 揖斐川町立揖斐小学校 関市立武芸小学校
<三重>
桑名市立多度中学校 同第五小学校 桑名高等女学校 朝日町立朝日小学校 四日市市立塩浜中学校 同南中学校 同楠中学校 同四日市高等女学校 同四日市商工学校 県立四日市高校 県立四日市工業高校 鈴鹿市立石薬師小学校 同箕田小学校 同平田野中学校 同神戸小学校(旧) 県立鈴鹿高等女学校 松阪市立機殿小学校 同花岡中学校 県立工業学校 県立松阪工業高校 県立飯南高等女学校 県立宮川高校 伊勢市立二見中学校 鳥羽市立鳥羽中学校 南勢町立五カ所小学校 大宮町・大台町学校組合立青陵中学校 県立名張高等女学校 三重師範学校 鈴鹿市立飯野小学校(旧)
<滋賀>
近江八幡市立八幡小学校
<奈良>
県立奈良高校 吉野町立吉野中学校 大宇陀町立大宇陀中学校 御杖村立神末小学校
<京都>
京都市立滋野中学校
<大阪>
大阪市立西船場小学校 大阪市立天王寺商業学校 大阪府立北野高校(旧)
<兵庫>
私立園田学園
<広島>
呉市立呉高等女学校
<山口>
下関市立下関商業高校
<佐賀>
小城市立小城中学校
<長崎>
新上五島町立上郷小学校
三重県内に校歌、歌碑以外で残るもの
孝子・万吉顕彰碑文(亀山市坂下)